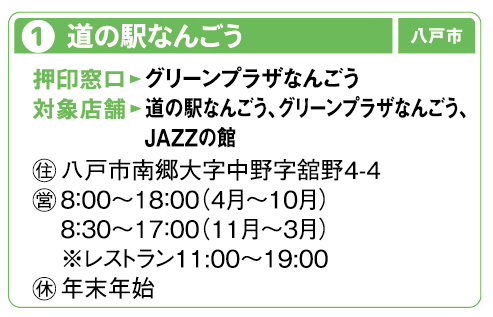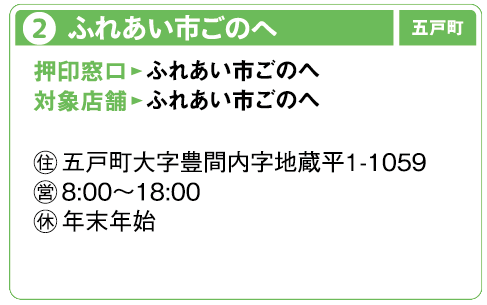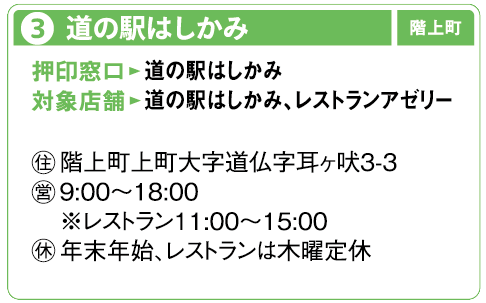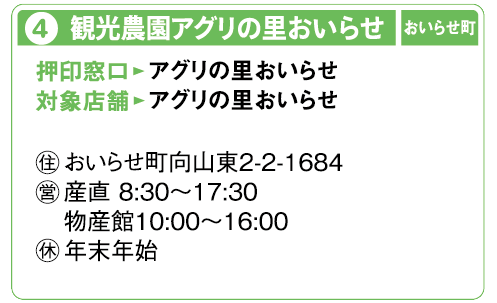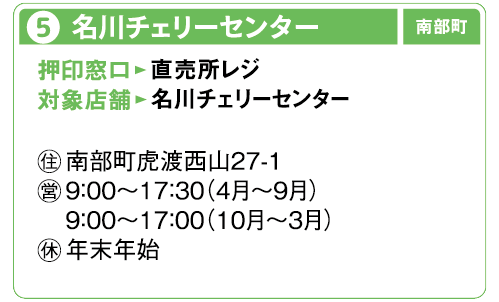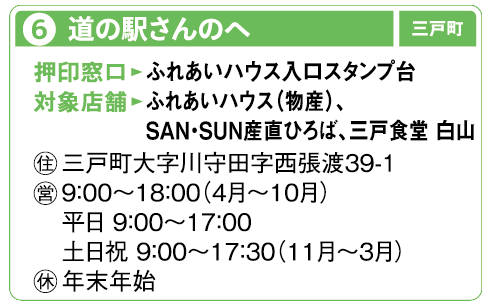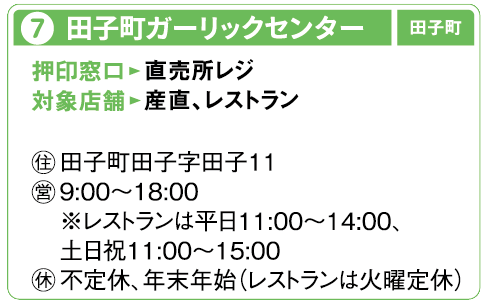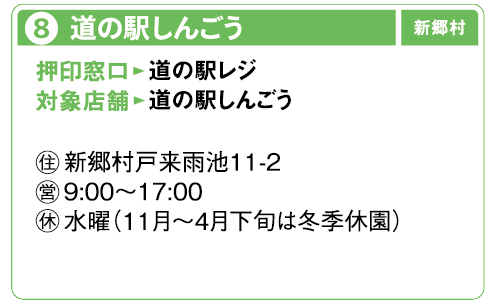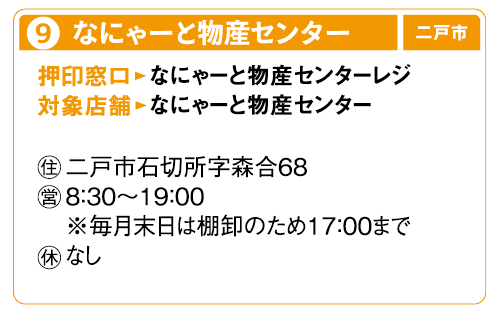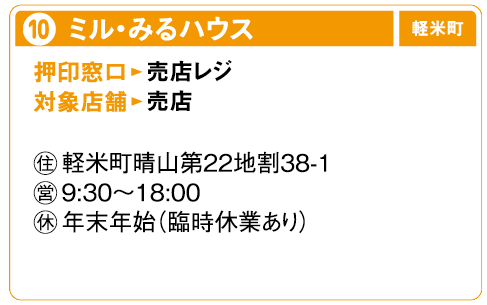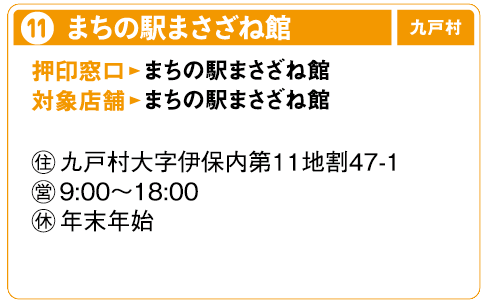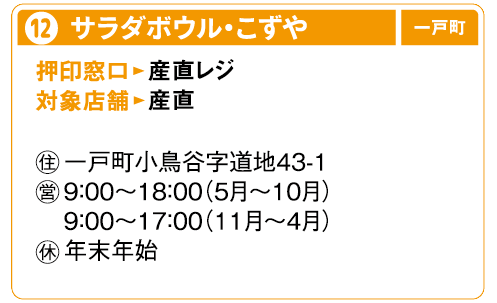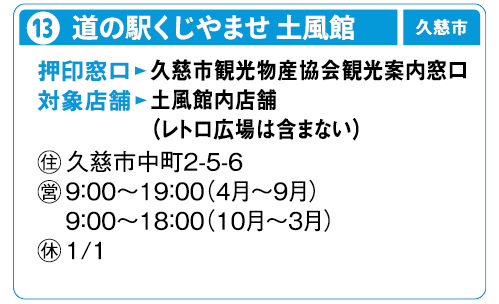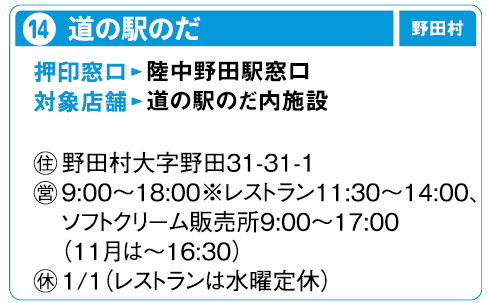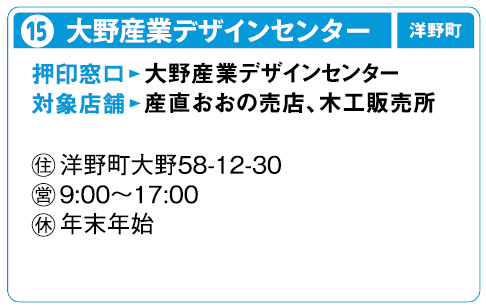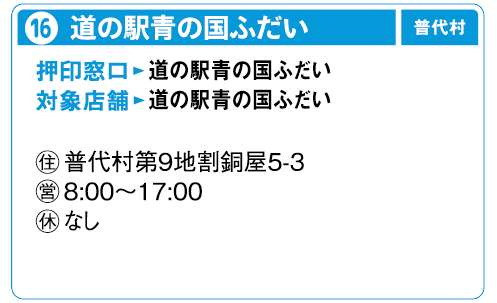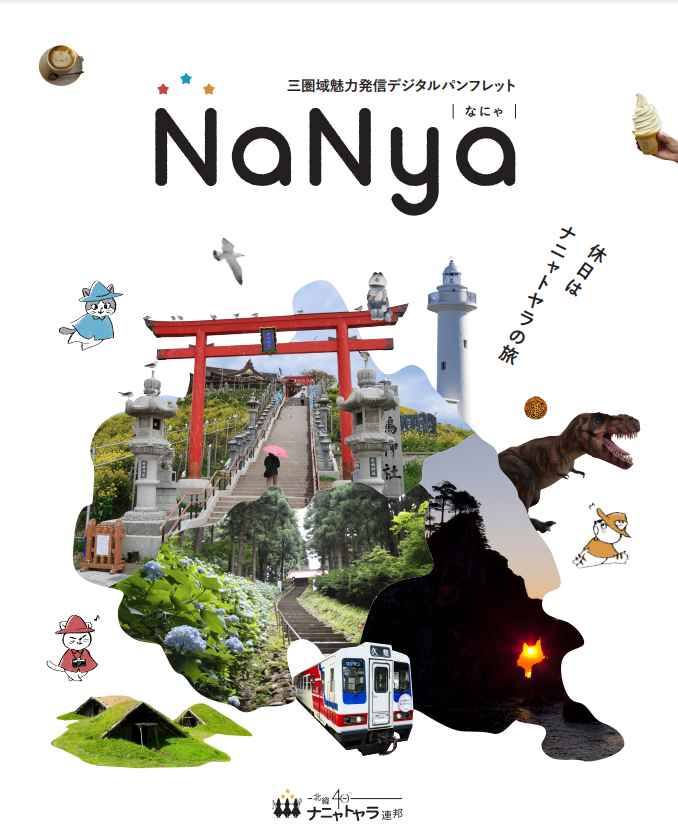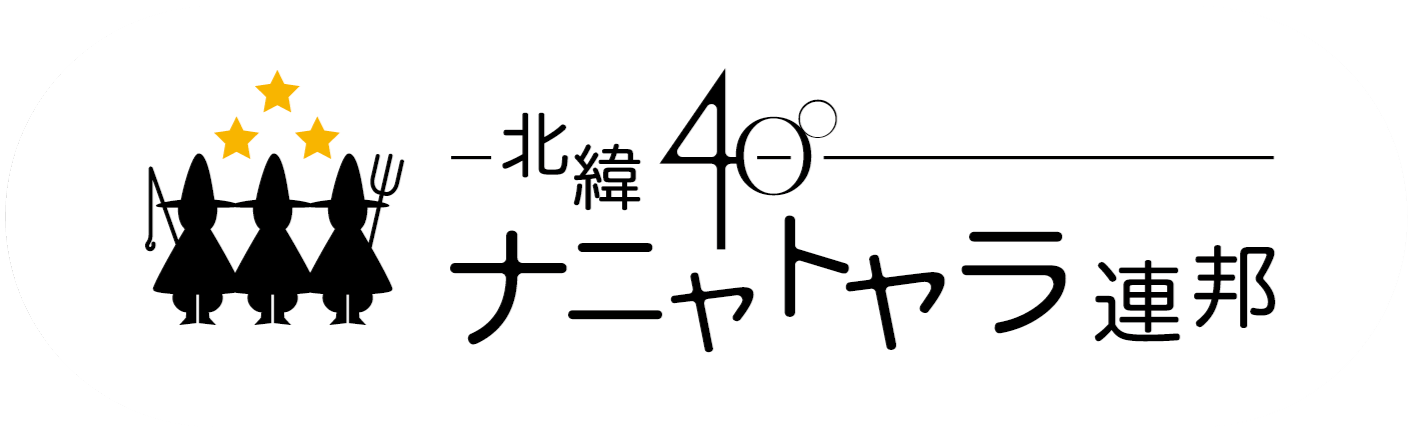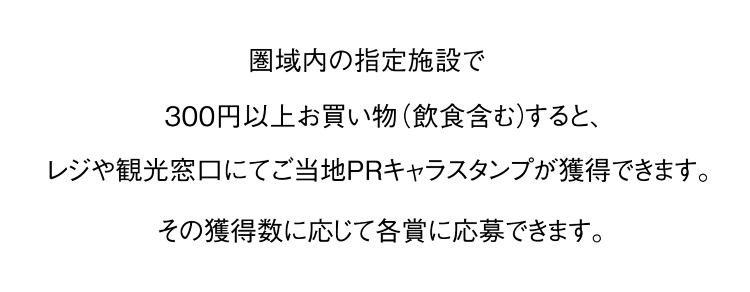
圏域内の指定施設で
300円以上のお買い物(飲食含む)すると、
レジや観光窓口にて
ご当地PRキャラスタンプが獲得できます。
その獲得数に応じて、
各賞に応募できます。

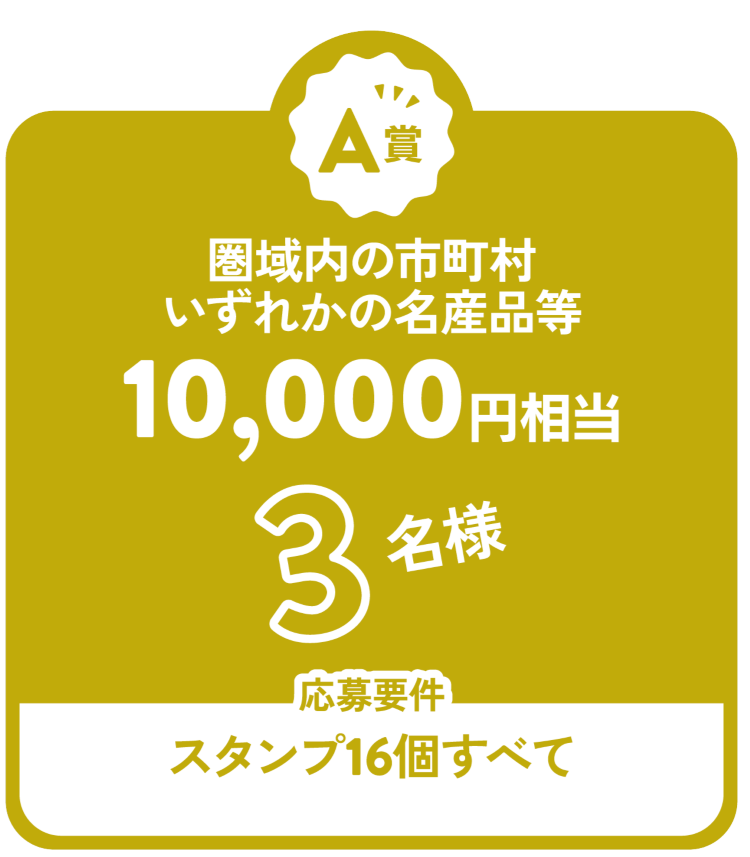
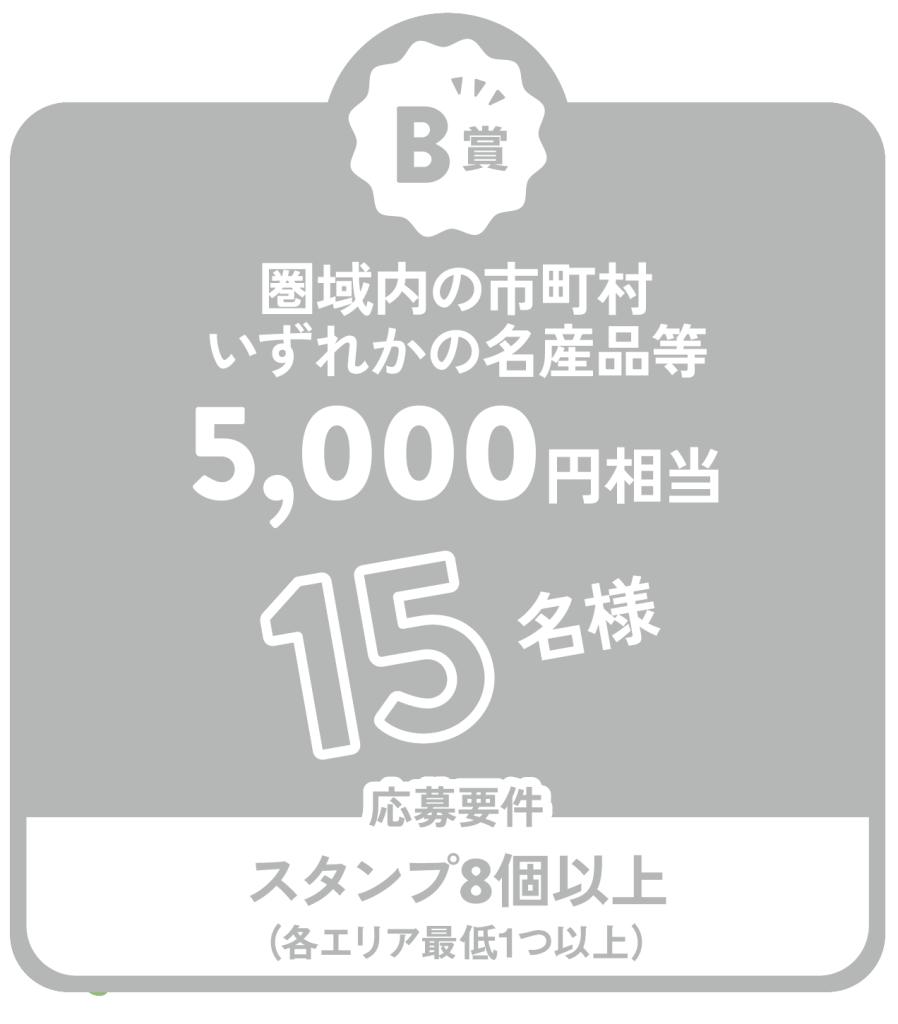

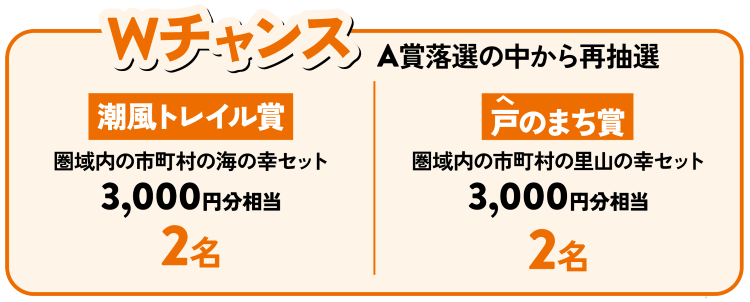

Xにおいて、部会公式アカウントをフォロー&「#ナニャトヤラリー」を付けて写真(ナニャトヤラ圏域内で買ったもの、食べたもの等)を投稿。スタンプラリー期間中に投稿した方の中から抽選で2名に圏域内の海の幸セットまたは里山の幸セット2,000円相当が当たります。
【参加方法】
①公式X
「@40_kouiki_kanko」をフォロー。
②ハッシュタグ
「#ナニャトヤラリー」を付けて投稿。
※発表は観光専門部会公式Xにて行います。

道の駅しんごうは11月~4月下旬まで冬季休園となります。
お出かけの際はご注意ください。
※各施設で営業時間・休館日が
異なりますのでご注意ください。
(営業時間外・休館日には
スタンプは押せません)
※各施設の直近の営業時間に
関しては、各施設のHPを
ご確認ください。